まずは基本から!連結決算って何のためにするの?(超入門)
連結決算とは?
一言でいうと、「親会社とその子会社(グループ会社)を、経済的に一つの組織とみなして作成する決算」のことです。
親会社単体の業績だけでなく、グループ全体の財政状態や経営成績を正しく報告するために行われます。上場企業にとっては、投資家への情報開示という面でも非常に重要なんですよ。
- 単体の決算と何が一番違うの?
-
一番の違いは、グループ会社間の取引(親子間での商品の売買やお金の貸し借りなど)を相殺消去したり、子会社の資産や負債を親会社の財務諸表に合算したりする「連結調整仕訳」が必要になる点です。これが少し複雑なんですよね。
- なぜ連結決算が必要なの?
-
例えば、親会社が子会社にたくさん商品を販売して利益を計上していても、グループ全体で見るとその商品はまだ外部に販売されていないかもしれません。単体の決算だけでは、グループ全体の本当の姿が見えにくくなってしまうため、連結決算で実態を明らかにする必要があるんです。
 アカリ
アカリ最初は「なんでこんな面倒なことを…」なんて思ってしまうかもしれませんが(笑)、グループ全体の力を正しく示すためには、とても大切な作業なんだと理解することが第一歩でした。
担当1年目でも大丈夫!連結決算の基本的な流れ(アカリが経験したステップ)
連結決算と聞くと、どこから手をつけていいか分からなくなりそうですよね。でも、一つひとつのステップに分解して見ていくと、全体の流れが見えてきます。私が担当1年目で経験した大まかな流れはこんな感じでした。
(※会社や使用しているシステムによって、細部は異なりますので、あくまで一例として参考にしてくださいね)
まずは、親会社と全ての子会社・関連会社から、それぞれの単体決算データ(試算表や財務諸表、その他連結に必要な情報がまとめられた「連結パッケージ」と呼ばれる資料など)を集めます。



ここで大切なのは、各社のデータの締め切りを守ってもらうことと、提出されたデータの正確性チェック!通貨が異なる海外子会社があれば、換算レートの確認も重要です。私は最初、このデータ収集とチェックに思ったより時間がかかって焦りました…。
集まった情報をもとに、どの会社を連結の範囲に含めるか(子会社として全て合算するか、関連会社として持分法を適用するかなど)を判定します。議決権の所有割合だけでなく、実質的な支配力なども考慮して判断するので、会計基準の知識が求められます。
ここが連結決算のメインイベント!グループ間の内部取引などを消去するための「連結調整仕訳」を行います。主なものとしては…
- 投資と資本の相殺消去:親会社の子会社への投資勘定と、子会社の資本勘定を相殺します。「のれん」や「負ののれん」が発生することも。
- 債権債務の相殺消去: 親子間の売掛金と買掛金、貸付金と借入金などを消去します。
- 投資と資本の相殺消去: 親会社の子会社への投資勘定と、子会社の資本勘定を相殺します。「のれん」や「負ののれん」が発生することも。
- 債権債務の相殺消去: 親子間の売掛金と買掛金、貸付金と借入金などを消去します。
- 内部取引高の相殺消去: 親子間の売上高と売上原価(仕入高)などを消去します。
- 未実現損益の消去:グループ会社間で販売された棚卸資産や固定資産に含まれる未実現利益(または損失)を消去します。



【ここが肝心!】連結決算を乗り切るための重要ポイント3つ(アカリ流)
さて、基本的な流れは掴めましたか?ここからは、私が担当1年目で「これは本当に大事だ!」と実感した、連結決算をスムーズに進めるための重要ポイントを3つお伝えします。
ポイント1:スケジュール命!関係会社・部署とのコミュニケーション術
Point1:徹底したスケジュール管理と、こまめな連携が成功の鍵
連結決算は、多くの関係会社や部署(子会社、海外拠点、監査法人、場合によっては経営企画部など)が関わる一大プロジェクトです。全体のスケジュールをしっかりと把握し、各担当者との情報共有や進捗確認を密に行うことが何よりも大切。
- キックオフミーティングの実施:連結決算開始前に、関係者を集めてスケジュール、提出資料、注意点などを共有。
- 進捗管理表の活用:誰がいつまでに何をするのかを明確にし、遅延がないか常にチェック。
- 定期的なミーティング:問題点や疑問点を早期に発見し、解決するために。
- 依頼は具体的に、丁寧に:相手に「何を」「いつまでに」「なぜ」必要なのかを明確に伝えることが、スムーズな協力を得るコツです。



私は最初、遠慮してしまってなかなか子会社の方に強く言えなかったりしたのですが…それでは全体の遅れに繋がってしまいます。「グループ全体で良い決算をする」という共通目標を意識して、言うべきことはハッキリ伝える勇気も必要だと学びました。
ポイント2:連結パッケージは宝の山?正確な情報収集のコツ
Point2:提出される「連結パッケージ」の精度が、連結決算の質を左右する
各社から提出される連結パッケージ(財務データや注記情報などがまとめられたもの)は、連結財務諸表を作成するための基礎となる、まさに「宝の山」。このデータの正確性が低いと、後々の修正作業が膨大になってしまいます。
- パッケージの記載要領を明確にする:誰が見ても分かるように、具体的な記載例や注意点を盛り込んだマニュアルを作成・共有。
- 提出前のセルフチェックを依頼する:各社で基本的なチェック(合計が合っているか、前期との大きな変動はないかなど)をしてもらう。
- 疑問点はすぐに確認する文化を作る:「こんな時どう書けばいいの?」と気軽に質問できる雰囲気づくりも大切。



特に海外子会社とのやり取りでは、会計基準の違いや言語の壁もあるので、丁寧なコミュニケーションと、提出されたデータの多角的なチェックが欠かせませんでした。
ポイント3:基礎固めと最新情報キャッチアップ!おすすめ勉強法
Point3:連結会計の基礎知識と、常にアップデートされる会計基準の学習は必須
連結決算は専門知識の塊です。基本的な連結仕訳のパターンを理解することはもちろん、会計基準は毎年のように改正されるため、最新情報をキャッチアップし続ける努力が不可欠。
- まずは良質な入門書を一冊読み込む:図解が多いものや、仕訳例が豊富なものがおすすめです。
- 会計基準の原文や解説を読む習慣をつける:企業会計基準委員会のサイトなどで公表されています。最初は難しくても、少しずつ慣れていきましょう。
- セミナーや勉強会に積極的に参加する:他の会社の事例を聞いたり、専門家から直接指導を受けたりするのも良い刺激になります。
- 社内のナレッジ共有を活用する:先輩や上司に積極的に質問したり、過去の調書や資料を参考にしたりするのも有効です。



私もまだまだ勉強中ですが、日々の業務で疑問に思ったことをそのままにせず、すぐに調べる癖をつけるようにしています。小さな積み重ねが、いつか大きな力になると信じて!
(今後の記事で、私が実際に参考にした書籍や勉強法についても詳しくご紹介できたらと思っています!)
連結決算を経験してアカリが感じたこと・成長できたこと



初めての連結決算は、正直言ってプレッシャーも大きかったですし、残業も増えました(苦笑)。でも、それを乗り越えたことで得られたものは、本当に大きかったと感じています。
グループ全体の数字を見ることで、個別の会社だけでは見えなかったビジネスの繋がりや課題が把握できるようになり、視野が一気に広がりました。また、多くの関係者と協力して一つのものを作り上げる達成感や、専門知識が深まることでの自信もつきました。
何より、「会社の全体像を把握し、経営に貢献できる仕事なんだ」という誇りを持てるようになったことが、私にとって一番の収穫かもしれません。
まとめ:連結決算は難しくない!ポイントを押さえてチャレンジしよう
今回は、連結決算の担当1年目だった私が押さえた基本的な流れと、失敗しないための重要ポイント3つについてお話ししました。
連結決算の基本的な流れ:
データ収集 → 連結範囲判定 → 連結調整仕訳 → 連結財務諸表作成 → 開示
重要ポイント3つ:
1. スケジュール管理とコミュニケーション
2. 正確な情報収集(連結パッケージの精度向上)
3. 基礎知識の習得と最新情報のキャッチアップ
連結決算は確かに複雑な業務ですが、一つひとつのステップを丁寧にこなし、ポイントを押さえて取り組めば、必ず乗り越えられます。そして、その経験はあなたの経理としてのキャリアを大きくステップアップさせてくれるはずです。
この記事が、これから連結決算に挑戦するあなたの不安を少しでも和らげ、前向きな一歩を踏み出すきっかけになれば幸いです。
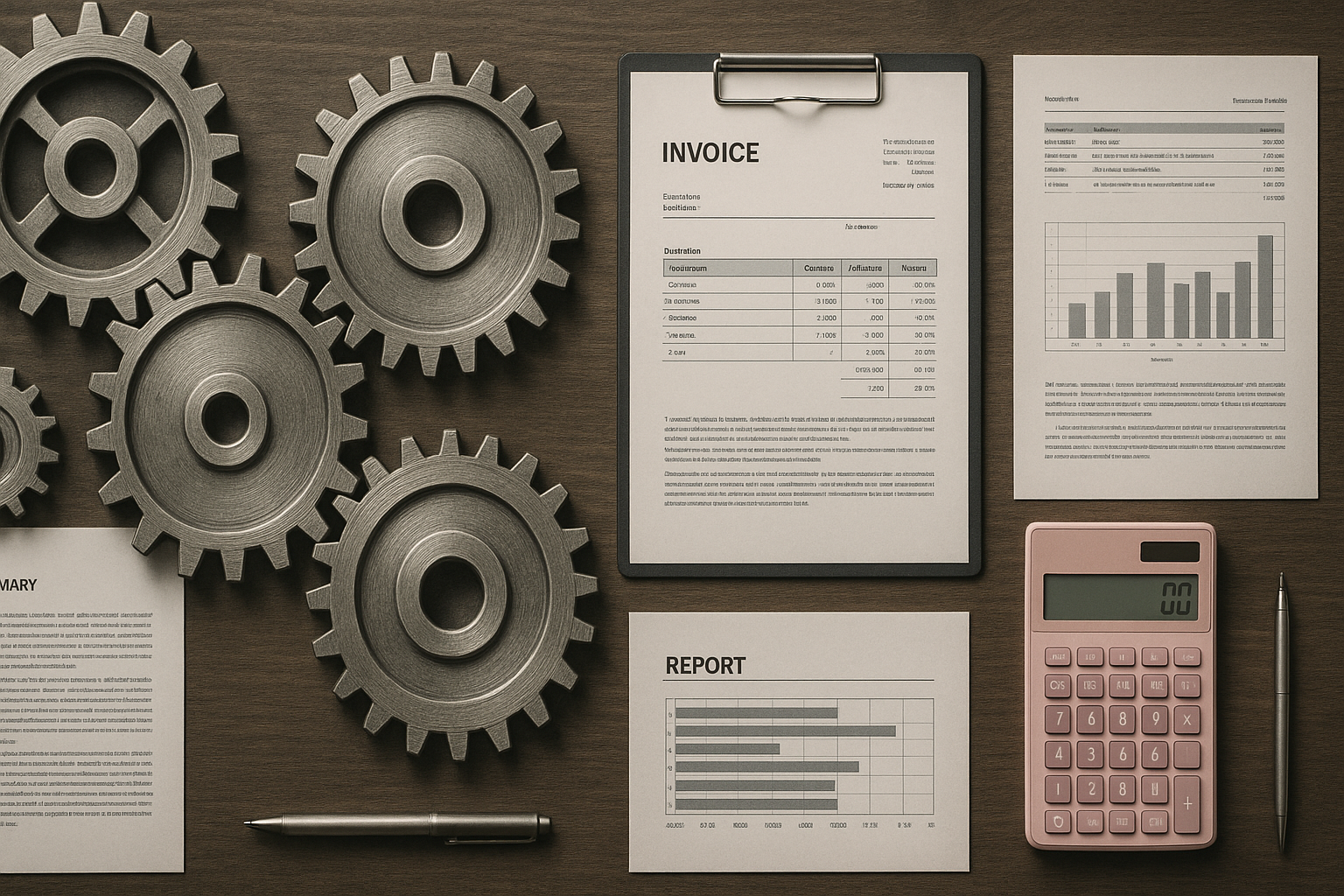


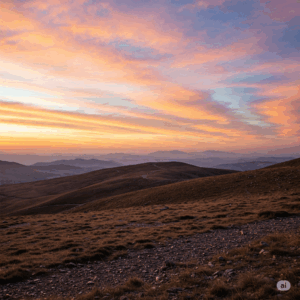
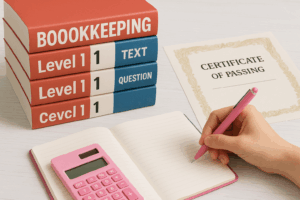

コメント